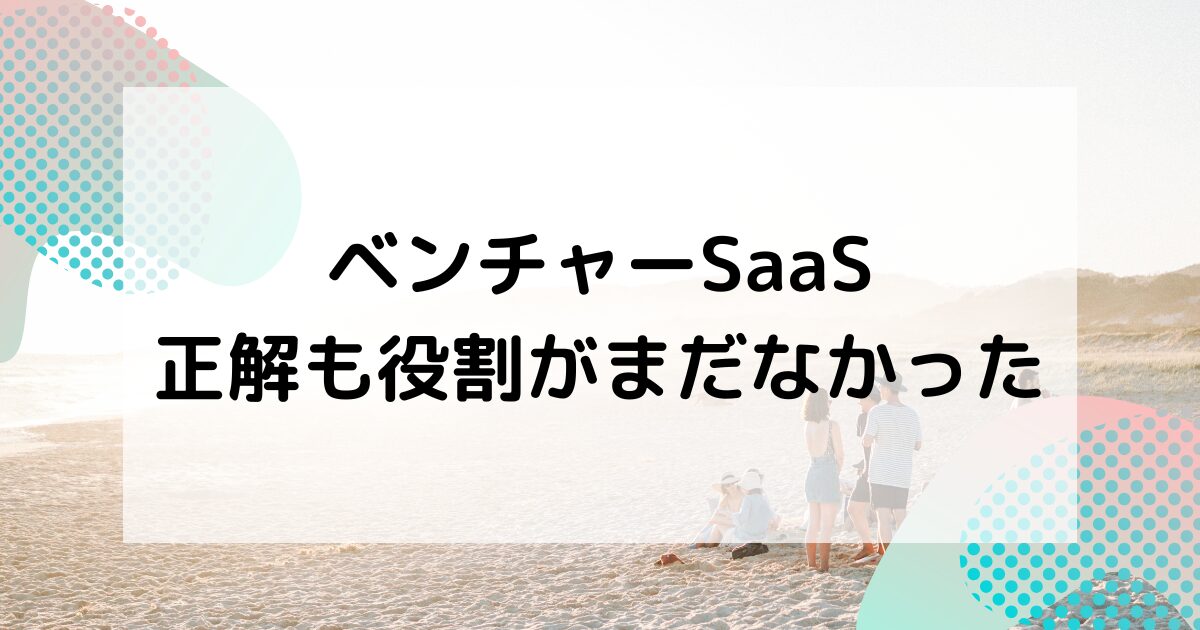SaaSに転職して最初に感じた違和感
転職初日。Slackのチャンネルに「ようこそ!」のスタンプが飛び交い、誰かがカジュアルに「何かあればいつでも聞いてくださいね」と声をかけてくれる。
……んだけど。
ふとした瞬間に、こんな疑問が湧いた。
「……で、私は今日、何をすればいいんだ?」
誰の部下?何のタスク?どこから始めるの?
最初に困ったのは、いわゆる「オンボーディング資料」が存在しなかったことだった。
マニュアルも、業務フローも、KPIも、特に説明されない。
なんとなくSlackを読みながら、「今は〇〇を進めてるっぽいな…」と探るしかない。
誰かが「これ、お願いできそう?」と軽く投げてきて、
それを拾ってみるけど、それがメイン業務なのかどうかも分からない。
「上司って誰になるんですかね?」と聞いたとき、
「一応、◯◯さんになるかな? まぁ横のつながりでやっていこう!」という返答で、
“あっ、この会社、本当に“できかけ”なんだ”と実感した。
前職では、やるべきことが決まっていた
営業として働いていた頃は、
- 明確なKPI(テレアポ◯件、訪問◯件)
- トークスクリプト
- 顧客情報の履歴
- チーム内でのロール分担
などが整っていた。
言い換えれば、「与えられる仕事」をこなせば評価される環境だった。
でも今は違う。
「自分が何をやるべきか」を、自分で決めなきゃいけない。
それも、社内に“まだない何か”を見つけて、提案して、動いて、形にしていく。
そんなフェーズに放り込まれていた。
やることが決まっていない=楽 ではなかった
正直に言うと、「自由で裁量がある会社」という言葉に少し期待していた。
でもその“自由”は、すべてを自分で定義しなきゃいけない不安定さと隣り合わせだった。
何が評価されるのかも分からない。
どの施策が正解なのかも分からない。
そして、周りも誰一人、はっきりとは答えを持っていない。
これは、“新しい業界でチャレンジしてる”とかいうレベルじゃない。
もはや、「一緒に地図を描くところから始めましょう」という世界だった。
想像以上に「仕組みがない」現場だった
SaaSに転職して驚いたのは、「営業経験が活かせるはず」という自信が、
ものの見事に打ち砕かれたことだった。
もちろん、前職でも泥臭い飛び込みや、法人営業でそれなりに鍛えられてきた。
ヒアリング力や提案力には多少なりとも自負があった。
でも、この立ち上げ期のSaaS企業には、そもそも“営業するための土台”が存在しなかった。
型がない。だから何も始められない
まず、トークスクリプトがない。
それどころか、何を訴求ポイントにするかも、実は定まっていない。
- サービスは形になりつつあるけど、まだ機能が変動中
- 顧客像が定まっておらず、ターゲットが毎週変わる
- 「今はとりあえず使ってもらう段階」なので、契約条件も流動的
という状況。
つまり、“売る”という行為以前に、「このプロダクト、誰にどんな価値を届けるのか?」という問いがまだ社内で整理されていない。
そしてそれを整えるのもまた、「現場メンバーの役割」だった。
提案資料も、見積もりのテンプレも、存在しない
営業という職種に就いていても、実際の仕事内容はほとんど“構築”に近かった。
- 提案資料はゼロから作る(ブランドトンマナも決まってない)
- ヒアリングした内容は、自分でNotionに整理して展開
- 社内で受注フローを聞こうとすると「たぶん◯◯さんが分かるかも」と言われる
あの頃の仕事の8割は、「前例を探す」か「誰かに聞く」だった。
前職では、資料を作りこむより、数字を追ってスピード重視の動きが求められていた。
でもここでは、“どう伝えるか”“どう残すか”“どう整えるか”がすべて自分の手に委ねられていた。
営業経験が“通用しなかった”のではなく、変換が必要だった
自分の中での“営業の型”は、整った環境がある前提で機能するものだった。
たとえば、
- 顧客にあわせてスライドをカスタマイズする
- CRMに沿ってステータス管理する
- チーム内で連携して案件をクロージングする
でも今は、そもそもスライドも、CRMも、チーム体制すら整っていない。
だから必要だったのは、“営業力”そのものではなく、
**「自分の経験を、ゼロからのフェーズにどう適応させるか」**という視点だった。
小まとめ:やることは山ほどあるけど、“決まってること”はほぼない
カオスな環境の中で、やる気が空回りすることもあった。
何をすれば評価されるか分からず、「自分は役に立ててるのか?」と不安になる日も多かった。
でも今思えば、これは「スキル不足」で詰んでいたのではなく、
“判断基準”や“進め方”を自分でつくる力が求められる世界だったのだと思う。
誰も悪くないけど、全員が手探りだった
このフェーズの一番の特徴は、「明確な指示がない」ことでした。
上司や役員も日々の課題に追われていて、戦略どころか、優先順位すら共有されていない。
“今この会社は、何を一番に目指しているのか”という問いに、誰もはっきり答えられないような空気感。
とはいえ、それが悪いわけではありません。
SaaSの立ち上げ期なんて、そもそも正解がない。
みんなで走りながら考えていくしかない。頭ではわかっていました。
でも、そんな中に放り込まれた自分は、明らかに迷っていました。
「何をすればいいですか?」が、誰にも聞けなかった
前職では、“決まってることをうまくやる”のが営業の仕事でした。
PDCAも組織に内蔵されていて、自分のやるべきことは明確。
やるべき量も成果も見えているから、走り方も分かりやすかった。
でもこの会社では違った。
「やることを見つけるところから始める」が仕事の本質だった。
何が問題なのか、何を改善すべきなのか、問いそのものを作らなければいけない。
しかも、まだプロダクトも社内連携も固まりきっていない。
苦手だったのは、自由じゃなくて“手がかりのなさ”
ここで気づいたのは、自分は完全にゼロの状態から何かを作り出すのが得意ではないということでした。
正解が曖昧すぎると、手が止まる。
何がゴールか分からないと、動く意味を見失う。
「自由にやっていいよ」という言葉が、プレッシャーにすら感じられたのは、
それが“自分に合っていないフェーズ”だったからです。
自分が活きるフェーズではなかった。けど、それを知らなかった
今振り返れば、そこはまさに「0→1」の真っ只中でした。
組織も、ルールも、評価軸も、すべてが曖昧な“混沌フェーズ”。
でも当時の僕は、それを“自分がダメだから成果が出ない”と受け止めていました。
「営業として使えない」「もっと主体的に動ける人にならなきゃ」と思い込み、空回りする日々。
ただ本当は、必要だったのは“努力”じゃなくて、“環境選びの視点”だったのだと思います。
小まとめ:「手探りの中で成果を出す」のは、誰にでも向いているわけじゃない
誰も悪くない。仕組みがないのも、指示がないのも、このフェーズなら当然。
でも、そこに適応しやすい人・しにくい人がいるのも事実。
自分がその場でうまくいかなかったのは、「能力不足」ではなく「特性とのミスマッチ」だった。
それを理解できたことが、のちに大きなヒントになっていきました。
自由にやっていいよ、の“本当の意味”
「自由にやっていいよ」
この言葉、最初はなんだかワクワクする響きに聞こえていました。
裁量がある、自分の判断で動ける、柔軟な環境。
でも現実には、「自由=何も決まっていない」ということだった。
やることは自分で決める。
成果も、提案も、動き方も、自分の中にある“問い”から始まる。
あのとき、ようやくその“自由”の意味に気づきました。
指示を待っていると、存在が透明になっていく
立ち上げ期のSaaSは、毎日が変化の連続です。
昨日動いていた仕組みが、今日にはもう破綻していることもある。
役員陣もプレイヤーとして目の前の顧客対応に追われていて、
「部下の成長を見守る」なんて余裕は正直ない。
だからこそ、“自分が何をしているか”を見せない限り、誰にも気づかれないんです。
- 指示を待っていても、誰も気づいてくれない
- 「こんなことを考えてます」と共有しなければ、存在感がない
- 動いたあとに、「なんでやったの?」と聞かれることもない
ここで気づきました。
このフェーズで評価されるのは、「完璧な成果」よりも**“自分から問いを立てて動いた痕跡”**だと。
仮説でもいい。動くと、見える景色が変わる
最初にやったのは、ものすごく小さな改善提案でした。
「FAQ、今のままだと顧客が迷う気がするので、項目を絞ってみてもいいですか?」
返ってきたのは、「あ、それいいね!お願い!」のひと言。
数時間後にはそれがチーム内で展開され、「これ使いやすいわ」と声が上がった。
そのとき実感したのは、正解じゃなくても動いた人が“見える”ようになるということ。
立ち上げ期は誰もが迷っている。だからこそ、
“とりあえずでも前に出た人”が次の流れをつくる存在になれる。
完璧な答えを出すより、「自分なりの問い」を持つこと
何をすればいいか分からないとき、役に立った考え方はこれでした。
「自分だったら、今この会社の何が気になるか?」
「目の前の業務、もっと楽にするには何ができるか?」
「顧客が困ってそうなことって、何だろう?」
こうした問いを自分の中に持つだけで、行動の選択肢が生まれる。
そして、それをチームにシェアするだけで、動きが生まれ、評価が始まる。
小まとめ:「自由にやっていいよ」は、放任じゃなくて“委任”だった
最初はしんどく感じた“自由”も、問いを立てて動き出してみると、
むしろその自由さが、自分の影響範囲を広げてくれました。
裁量があるというのは、ただ好きにやれることじゃなくて、
「この組織にとって何が必要か」を自分で考えて、動いて、見せる責任があるということ。
「何をすればいいか分からない」から、「これをやる」に変えた瞬間
何をすればいいか分からない——。
あの混沌とした初期フェーズでは、常にその不安がつきまとっていました。
けれど、あるときから気持ちが少しずつ前を向きはじめました。
「これをやろう」と自分で動けるようになった瞬間が、いくつかあったんです。
最初の一歩は、“小さく手を動かす”だった
とにかく、完璧を目指すのをやめました。
まずは身の回りの「気になること」「不便なこと」を洗い出してみる。
- よく使うSlackテンプレが見つからない
- 顧客からの同じ質問に何度も回答している
- チームのタスク管理が人によってバラバラ
このあたりをNotionにメモしていき、
「じゃあ、これ1個だけ直してみよう」と手を動かしました。
すると、誰かが「それいいね」と言ってくれて、
小さな改善がちょっとずつチームに浸透していきました。
仮説→実行→フィードバック のサイクルで“思考の筋肉”がついてきた
次第に、動き方にパターンが出てきました。
- 課題を観察する
- 仮説を立てる(たぶん、これが原因?)
- 小さく実行する
- 周囲の反応を観る・数値を追う
- 修正 or 継続する
これを繰り返すうちに、「動いて考える」ことへの抵抗がなくなってきたんです。
“答えを探す”より、“仮説を立てて試す”方が早く、確実で、納得もできる。
「とりあえずやってみる」が怖くなくなったのは、このサイクルが体に馴染んできたからだと思います。
評価されたのは「答え」ではなく「姿勢」だった
この頃から、少しずつ上司や役員との会話にも変化が出てきました。
「この前のSlackテンプレ、めっちゃ便利だったよ」
「最近、動きが見えてきて安心してるよ」
驚いたのは、“正解かどうか”よりも、「考えて動いた形跡」が評価されていたことでした。
完璧な戦略も、KPI達成もできていない。
でも、自分で問題を見つけて、自分の言葉で仮説を立てて、自分なりの手で修正をしていた。
それが「信頼」に変わっていったんです。
小まとめ:「動く前に考える」より、「動きながら考える」
立ち上げ期のSaaSでは、準備万端の人よりも、まず手を動かせる人の方が速く適応していきます。
不完全でも、試してみる。
ダメならすぐに直す。
その繰り返しが、いつの間にか周囲の信頼になっていた。
混乱の中でも、評価された動き方の共通点
環境が整っていない。
正解も決まっていない。
役職も関係なく、全員が手探りで走っている。
そんなカオスな立ち上げ期でも、不思議と“信頼される人”には共通点がありました。
そして振り返ると、自分も少しずつその動き方にシフトしていったことで、周囲からの扱いが変わっていったのを感じています。
1. 「答え」ではなく「仮説」で話す
このフェーズでは、完璧な提案なんて求められていませんでした。
むしろ、「自分なりにこう考えた」という仮説ベースの会話ができることが大事でした。
- 「今のお客さん、たぶんこういう課題を感じてると思います」
- 「これ試してみたいんですが、優先度的にアリですか?」
- 「こっちの資料の方が伝わりやすいかも、と思ってます」
この“◯◯かもしれない”レベルの発信が、動きの起点として歓迎される空気があった。
確実じゃなくていい。
とにかく考えて、形にしようとしている人は目立つし、頼られる。
2. 情報を整理して「見える化」する力
SaaS立ち上げ期で意外と重宝されたのが、情報を整えて共有できる力でした。
- 会議で出た話をNotionに整理して「次にやること」を明文化
- Slackで埋もれたナレッジを集約し、共有ドキュメントにまとめる
- 顧客とのやりとりを構造化して報告し、再利用可能な形にする
こういう動きは、直接売上につながらなくても、チーム全体にとって“助かる”んです。
そして、整える力を持つ人のところに、自然と相談が集まってくるようになる。
3. 小さく動いて、小さく共有する
評価されている人の特徴は、「でかいことを言わない」ことでもありました。
- 「これ、ちょっと整理してみました」
- 「仮で作ってみたんですが、違和感あったら直します」
- 「一旦、3件だけヒアリングしてみたので、内容見てもらえますか?」
大きな企画よりも、小さく動いて小さく共有する人のほうが、現場を回す存在になっていく。
フィードバックももらいやすいし、軌道修正もしやすい。
それが結果的に、チームの“循環”をつくる役割になっていくのだと思います。
小まとめ:不安定な状況では、信頼される行動は“姿勢と構造”
カオスな組織では、評価軸も曖昧です。
だからこそ、
- 仮説を立てて動けること
- 情報を整理し、見える形で渡せること
- 相談できる状態で“途中共有”できること
こうした動き方が、誰よりも目立つし、助けられる。
その積み重ねが「この人がいれば大丈夫」という信頼に変わっていきます。
カオスな立ち上げ期だからこそ、自分の働き方の軸が見えた
当時は毎日、正直きつかったです。
何が正解か分からないまま動いて、成果も曖昧で、自信が持てない。
でも、あの「何も決まっていない場所」にいた時間があったからこそ、今は自分の“働き方の軸”をちゃんと持てるようになりました。
「自分が得意なフェーズ」と「苦手なフェーズ」がはっきりした
今なら分かります。
私は、ゼロから立ち上げるタイプではなく、1→10の中で力を発揮するタイプだということ。
- ある程度の型や枠組みがある中で
- バラつきを整えたり、再現性を持たせたり
- 現場の声を拾って改善策を仕組みに落としたり
こうしたことに取り組んでいるとき、自分は楽しく、自然に成果も出やすい。
逆に、目的もゴールも曖昧な状態から「何をするか」を探るフェーズでは、思考が止まりがちだった。
あの混沌を経験しなければ、自分が“どこで戦うと強いか”なんて分からなかったと思います。
過去の経験が、少しずつ点と点でつながってきた
- 大手メーカーで、決められた型の中で営業をしていた日々
- 仕組みのないSaaSベンチャーで、自分の無力さを突きつけられたこと
- 型のあるインサイドセールスで、目標を追いかける楽しさを再発見したこと
- 社内向けのCS業務で、“整える力”を評価されたこと
そして今、大手SaaS企業で、ある程度枠組みがある中で「お客さんの成果を最大化する方法」を模索するCS業務に就いています。
決まっている中で、自分なりの改善を加えていく。
“整った環境”があるからこそ、“自分の武器”が活きるようになったんです。
適応できなかった経験も、ちゃんと活きている
0→1の環境で苦しんだあの時間も、今ではちゃんと意味を持っています。
曖昧な状況でも、問いを立てて動く力。
完璧じゃなくても、まず手を動かす勇気。
“自分の苦手”を冷静に理解し、無理に背伸びしない戦い方を知ったこと。
だから今、別の環境に行っても、ちゃんと自分のポジションを作っていける感覚があります。
最後に
転職は、職種や企業を変える行為だけれど、
本当の意味でキャリアを前に進めるのは、「自分の扱い方」を知ることだと思います。
- 自分はどんなフェーズで活きるのか
- 何をしていると楽しくて、結果が出やすいのか
- 逆に、どんな環境では苦しくなりやすいのか
これを知っているだけで、次に迷ったときの選択が圧倒的にラクになります。
カオスなSaaSに飛び込んでよかった。
うまくいかなかったけど、あの経験があったから、今がある。
そう思える今なら、「あの頃の自分」にも、ちゃんと感謝できます。