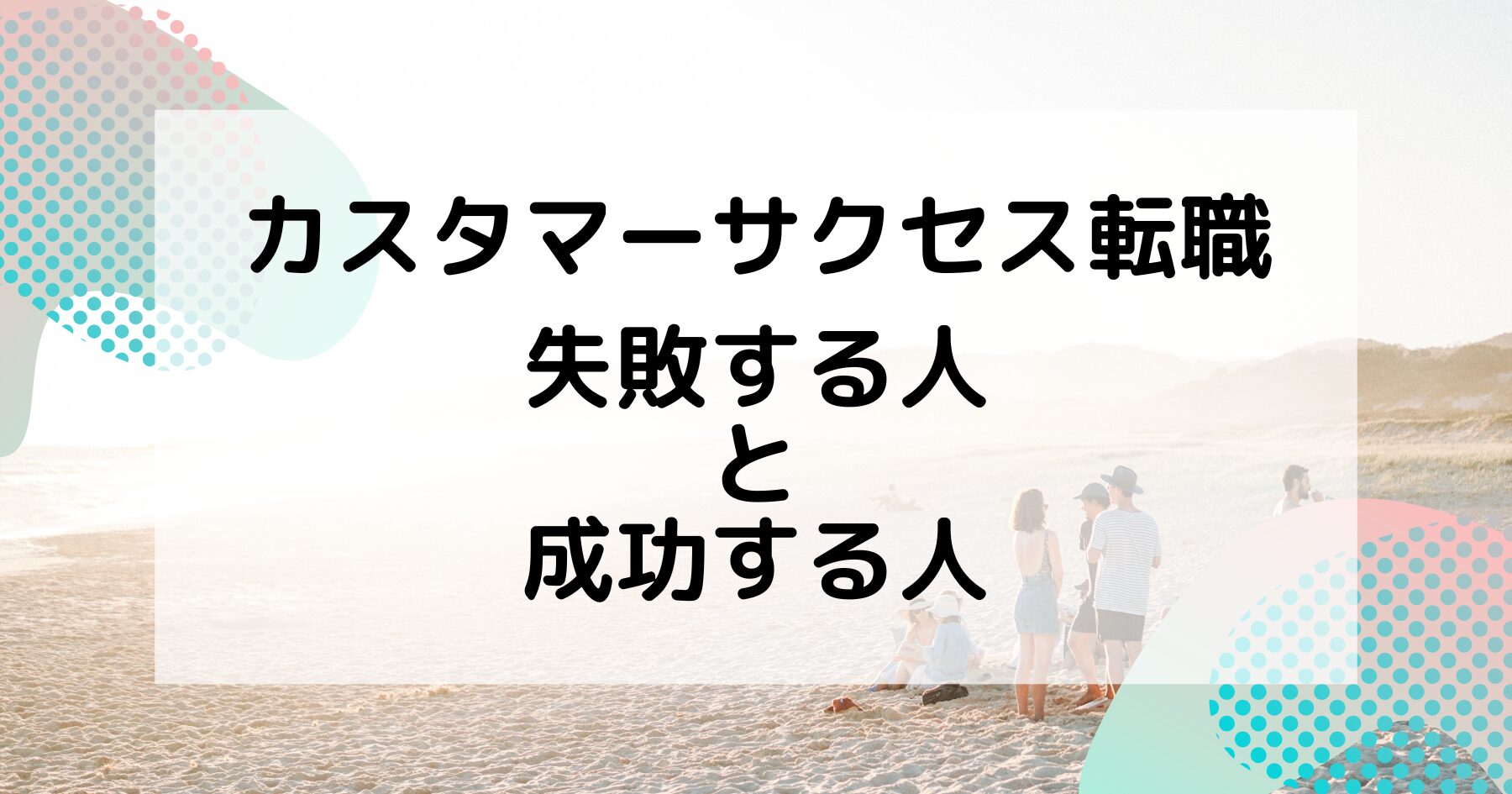営業職からカスタマーサクセスに転職して、今年で6年目になります。
これまでSaaS企業を4社経験し、どこでも「営業出身」の同僚たちと一緒にCSチームを立ち上げたり、育てたりしてきました。
でも、正直な話をすると——
営業でバリバリ活躍していた人が、カスタマーサクセスに来て詰まってしまう姿を、何度も見てきました。
逆に、「あれ、この人そんなに営業得意そうじゃなかったのに…」というタイプが、CSではぐんぐん成果を出していたりもします。
この違いって何だと思いますか?
この記事では、私自身の実体験や、これまで見てきた仲間たちの姿をもとに、
営業出身者がCSでつまずいてしまう理由、そしてその壁を乗り越えた人の共通点についてお伝えします。
「売る仕事はもういい。でも、誰かの成果に寄り添いたい」
そんな気持ちを持っている方にこそ、読んでほしい内容です。
なぜ営業経験者がCSで詰みやすいのか?背景とギャップ
カスタマーサクセス(以下、CS)は、近年営業職からの転職先として注目を集めています。
「売るより支えるほうが向いていそう」「数字のプレッシャーから解放されたい」
このような理由でCSを目指す方は少なくありません。
しかし実際には、営業からCSに転職してすぐに「思っていたのと違った」と悩む方も多く見られます。
なぜ営業経験者がCSで詰まりやすいのか。その背景には、いくつかの落とし穴が存在します。
「営業経験があれば活かせる」は本当。ただし、半分はウソです
CSは、たしかに営業職と似た部分があります。
しかし、“似ている”と“同じである”は別物です。この差を見誤ると、CSで苦労することになります。
営業出身者がよく抱きがちなCSのイメージ
- クロージングがないから楽そう
- 関係構築スキルがあれば十分
- 数字のプレッシャーがないので穏やかに働ける
一方で、実際のカスタマーサクセスでは以下のような力が求められます。
実際に必要とされるスキル・姿勢
- 売らずに成果を出す力(継続利用・活用促進・アップセル)
- 顧客の業務理解とプロダクト知識
- 複数顧客を同時に対応するスケジューリング力
- トラブル発生時に“感情の受け皿”になれる対応力
つまり、営業とは土俵も、勝ちパターンも違うのです。
ギャップを生む3つの典型的な誤解
ここからは、営業職からCSに転職した方がよく陥る“勘違い”を整理します。
1. 「売らなくていい=楽」は誤解です
CSでは契約や数字のノルマがない場合もあります。
しかし、その代わりに顧客の「成功」に対する責任が課されます。
相手が成果を出せないと、こちらの評価が落ちる——それがCSのリアルです。
2. 「コミュニケーション力があれば通用する」は危険です
たしかに営業で培ったトーク力や人間関係構築力は武器になります。
ただしCSでは、それだけでなく以下のような力が求められます。
- 論理的に課題を整理する力
- 問題の本質を引き出すヒアリング力
- 顧客の業務プロセスを理解する力
いわば、「仲良くなる」よりも「一緒に課題を解く」スキルが重視されます。
3. 「顧客対応=サポート」と考えるのは危険です
CSは、問い合わせに対応する“受け身のサポート”ではありません。
顧客の“まだ言葉になっていない課題”に気づき、先回りして価値提案を行う、能動的なパートナーです。
「困っていない顧客」にも働きかける必要がある点で、まったく別物と言えます。
営業マインドを引きずるほど、CSでは苦しくなります
営業職では「数値目標」「受注」という短期成果が明確でした。
一方でCSは、「導入効果」「長期継続」「顧客満足度」など目に見えにくい成果が軸になります。
そのため、
- すぐに結果が見えない
- 評価指標があいまいに感じる
- 成果が“顧客の行動次第”というジレンマを感じる
このような“手応えのなさ”に戸惑い、ストレスを感じてしまうケースが多いのです。
小まとめ:CSという仕事の本質を理解する
- CSは、顧客の成功を支える「攻めの支援者」です
- 成果は「売ること」ではなく、「成果を出してもらうこと」
- 営業スキルは活かせますが、“営業的な勝ちパターン”が通じるとは限りません
この章で、少しでも「自分の思っていたCSと違うかもしれない」と感じたなら、それは大きな一歩です。
次章では、営業とCSでどのように求められるスキルやマインドが違うのかをより具体的に掘り下げていきます。
営業とCSでは“戦う土俵”が違う:求められるマインドとスキルの違い
営業からCSへ転職する際、多くの人が「近い職種だからなんとかなるだろう」と考えます。
しかし実際には、「近いどころか、やっていることも評価されるポイントも全然違った」と感じるケースが非常に多いです。
ここでは、**営業とCSの「土俵の違い」**をマインド面とスキル面の両面から整理していきます。
営業の土俵:短期決戦で数字を追う仕事
営業職の評価軸は明快です。
売れたか、売れなかったか。それに尽きます。
- 明確な数値目標(売上・件数など)
- クロージングまでが主戦場
- 顧客との関係は“購入”をゴールとした一時的なもの
- 競合との比較、値段交渉なども頻発
成果が即座に数字で現れやすいため、**“わかりやすい達成感”**が得られる仕事です。
CSの土俵:中長期視点で顧客と並走する仕事
一方で、カスタマーサクセスは顧客との関係性が“契約後”に始まります。
そしてその関係は、以下のような特徴を持ちます。
- 評価軸は「活用度」「継続率」「顧客満足度」など定性的なものが多い
- クロージングはせず、“使い続けてもらう”ための伴走
- 顧客の業務フローや目標達成に深く入り込む
- 「売る」より「気づかせる」「支える」力が重要
つまり、“売って終わり”から“使って始まり”へという、真逆のサイクルが求められます。
営業とCSに求められるスキルの主な違い
| 項目 | 営業 | カスタマーサクセス |
|---|---|---|
| 評価基準 | 売上・契約件数 | 利用継続率・活用状況・満足度 |
| コミュニケーション | 交渉力・クロージング力 | 傾聴力・信頼構築・課題抽出力 |
| マインドセット | 数字を追う/ゴールは契約 | 顧客視点で考える/ゴールは成功の実現 |
| スキルの方向性 | 外向き・攻撃的(売り込む) | 内向き・分析的(使ってもらう支援をする) |
| ゴールの時間軸 | 短期(今月の数字) | 中長期(数ヶ月〜年間での継続と成果) |
実際にCSで重宝されるスキルとは?
営業経験が活かせる場面は確かにありますが、CSで評価されるスキルは以下のようなものが中心になります。
1. 傾聴力と課題発見力
顧客が言語化していない課題を、会話や利用状況から察知する力です。
「〇〇が使いにくい」といった表面的な声ではなく、背景にある業務フローや目的にまで踏み込んで考えることが求められます。
2. 顧客の成功定義を共に設計する力
CSでは、顧客ごとに“何が成功か”が異なります。
「この企業にとって、何を達成することがゴールなのか?」を一緒に考える、コンサル的な視点が重要です。
3. 継続的な信頼構築スキル
営業では“第一印象”や“即効性のあるアプローチ”が重視されがちですが、CSでは**“関係の質と深さ”が全て**です。
特に導入後3ヶ月〜半年の期間で、「この人がいれば安心」と思わせられるかが分かれ道になります。
マインドの切り替えが鍵
営業で結果を出してきた人ほど、無意識に「売るための思考回路」が染みついています。
CSではそれをいったんリセットし、以下のように考え方を切り替える必要があります。
- 契約=ゴール → 契約=スタート
- 数字で動く → 信頼と成果で動く
- 顧客を説得する → 顧客と一緒に考える
このマインドセットが変えられないと、CSではどこか空回りしてしまいます。
小まとめ:営業とは「似て非なるもの」と捉える
- 営業は“売る力”がメイン、CSは“使ってもらう力”がメイン
- 成果の見え方・出し方・評価基準が根本的に違う
- 価値の伝え方も、「これが良い」ではなく「こう使えば成果が出せる」へ
詰む人の共通点:うまくいかない人が見落としてること
カスタマーサクセスは「営業より穏やかそう」「コミュニケーション能力があればいける」といった印象から、比較的“行きやすい職種”と思われがちです。
しかし、いざ転職してみると
「なんか自分だけ浮いてる気がする」
「やってることが正しいのか分からない」
といった違和感にぶつかり、やがてモチベーションを失ってしまう——
これはよくあるパターンです。
ここでは、営業出身者がCSで“詰んでしまう”ときに共通して陥っているポイントを整理してみましょう。
よくある詰まりパターン4選
1. 成果が見えにくくてモヤモヤする
営業時代は「受注=成果」と明確でした。
一方でCSは、成果が“じわじわと”現れる仕事です。
例えば、
- 顧客が製品を使い続ける
- アップセルのきっかけが生まれる
- 「この機能が役に立った」と言ってもらえる
こうした成果は、時に半年〜1年後にようやく形になります。
そのため、短期での達成感や評価に慣れていた人ほど、自分が役に立っている実感を持ちにくくなります。
2. 指示待ちではついていけない
CSは業務範囲が広く、やるべきことが曖昧になりがちです。
たとえば、
- 「今月どの顧客を重点フォローすべきか?」
- 「このクライアントが抱えてる“まだ見えてない課題”は何か?」
- 「ツールの使い方よりも、業務改善の話にどうつなげるか?」
これらはマニュアルでは教えてもらえません。
自分で考え、仮説を立て、試していく姿勢がないと置いていかれます。
営業時代に「とりあえずアポ取って言われた通りに動いていた」というタイプは、ここでつまずきやすいです。
3. サポート業務に寄りすぎて“便利屋”になる
CSを「問い合わせ対応係」や「手順説明担当」として捉えてしまうと、
気づけば「操作案内」や「トラブル受付」の役回りばかりになってしまいます。
それでは、CSとしての本質——
顧客の“成果”を生み出す支援にはつながりません。
以下のような傾向があると危険信号です:
- 問い合わせが来るまで放置
- 説明ばかりで、提案や伴走がない
- 顧客の“目的”を知らずに対応している
CSは、「使い方」ではなく「使いこなし方」を共に考える存在であるべきです。
4. 顧客に“気づかせる力”が足りない
営業では、課題がある顧客に対して解決策を提案する力が求められていました。
しかしCSでは、「顧客自身が気づいていない課題」を一緒に発見する力が必要になります。
この“気づき力”が弱いと、以下のような悪循環に陥ります:
- 顧客は本音を語らない
- 表面的な相談ばかりされる
- 利用も定着せず、結果として解約に…
大切なのは、「この人なら自分の課題を一緒に考えてくれる」と思わせられる信頼と視点です。
詰む前に、自分に問い直してみてほしいこと
以下の問いを、自分にぶつけてみてください。
- 今、自分が支援している顧客は「何を目指しているのか」言えるか?
- 自分の仕事は、その“顧客の成功”にどうつながっているのか?
- 顧客がうまくいかなかったとき、誰の責任だと考えるか?
この問いに詰まるようであれば、まだ営業的な思考から抜け出せていない可能性があります。
小まとめ:うまくいかない人ほど、CSの“本質”を見ていない
- 成果の“定義”があいまいでも、考え続ける覚悟があるか
- 顧客の“気づいていない課題”に寄り添う視点があるか
- 指示を待たず、自分の頭で“行動設計”できるか
これらは、営業出身者がCSで成功するための最低ラインとも言えます。
乗り越えた人はここが違う:活躍するCS経験者の思考と習慣
営業出身者の中でも、カスタマーサクセス(CS)でしっかり成果を出している人たちがいます。
その人たちは、特別なスキルを持っていたわけでも、最初から適性があったわけでもありません。
ただ、いくつかの**共通した“切り替え”と“行動習慣”**を身につけていたのです。
この章では、営業からCSに転職し、現場で評価されている人たちが実践しているポイントを紹介します。
共通点①:「売らずに成果を出す」ことに腹落ちしている
営業の成果は「契約」。一方、CSの成果は「顧客が継続して使い、成功すること」です。
この違いに納得できず、営業時代の感覚を引きずってしまう人は、CSで苦しくなります。
一方、活躍している人はこう考えています。
- 「売らなくても、価値は伝えられる」
- 「契約がゴールではなく、スタートだ」
- 「“この人がいれば成果が出る”と顧客に思わせるのが本当の成果」
つまり、自分の“存在価値”の再定義をきちんと行っています。
共通点②:「課題を引き出す」ではなく「掘り下げる」力がある
CSで成果を出す人は、顧客からの相談を“そのまま鵜呑みにする”ことはしません。
むしろ、相手の言葉の裏にある「真の課題」を探る習慣が身についています。
たとえば、
「操作が難しくて使えない」と言われたとき、
単に操作方法を教えるだけでは不十分です。
優秀なCSはこう考えます:
- 「なぜその機能を使おうとしたのか?」
- 「そもそも、その機能は本当に必要だったのか?」
- 「その裏に業務上のどんなストレスがあるのか?」
こうして、表面的な不満を、価値提供のチャンスに変えていきます。
共通点③:成果を“自分で定義する力”がある
CSの仕事は、明確な数字で評価されにくいことも多いです。
だからこそ、活躍している人ほど「自分の仕事がどう価値に貢献しているか」を、自分の言葉で語れます。
たとえば:
- 「3ヶ月以内に定着率が70%を切りそうな企業に、成功体験を最初に1つ届ける」
- 「アップセル可能性の高いクライアントを、毎月2件発掘して担当営業と連携する」
これらは数字ではなくても、“動き方”として成果を設計しているのが特徴です。
共通点④:愛される、でも甘やかさない“プロっぽさ”がある
CSは、営業よりも顧客と長く・深く付き合う職種です。
その中で、単に「優しい人」「気の利く人」では終わらず、“頼れるビジネスパートナー”として認識されているかが分かれ道になります。
信頼されるCSは、こんな行動を取っています:
- 顧客の目標に寄り添い、視座を引き上げてくれる
- イエスマンではなく、時に「それは違います」と言える
- 問題が起きたとき、“感情の受け止め”と“論理の整理”の両方ができる
つまり、情のある伴走者でありながら、距離感と専門性を保ったプロとして振る舞える人です。
活躍する人は「営業経験」を活かす場所を選んでいる
最後に重要なことを一つ。
CSで活躍している人たちは、自分の営業スキルを“そのまま”ではなく、“変換”して使っています。
たとえば:
- クロージング → 活用提案
- スクリプト力 → 課題整理シートの作成
- ヒアリング → サクセスプラン作成
「売る力を手放す」のではなく、「活かし方を変える」ことができた人が成功しているのです。
小まとめ:転職のその先で力を発揮する人の共通点
- 成果の定義を、自分で再設計できる
- 顧客の言葉を“掘り下げて”、価値につなげられる
- 感情と論理、両方に寄り添える人間力がある
- 営業スキルを「使い回す」のではなく、「変換する」視点を持っている
次章では、こうした活躍人材を求める企業側の本音に迫ります。
営業経験者に対して、CS職としてどんな期待を寄せているのか? どこに“価値”を見ているのか?
その視点を知ることで、転職先選びの精度も上がるはずです。
企業が営業経験者に“本当に求めていること”とは?
カスタマーサクセス(CS)の求人には、「営業経験歓迎」と記載されていることがよくあります。
ですがその一方で、営業出身者がCS職に就いてから、**「思ったより評価されない」「期待されていた役割とズレていた」**と感じるケースも少なくありません。
企業はなぜ営業経験者を欲しがるのか?
そして、どんな“価値の出し方”を求めているのか?
ここでは、企業側の目線から読み解いていきます。
企業が営業出身者に感じている3つの期待
まず前提として、企業が営業経験者に期待しているのは、単なる“過去の成果”ではありません。
彼らは、「この人ならCSとして顧客と成果をつくってくれそうだ」という**“ポテンシャルと応用力”**を見ています。
1. 顧客と“信頼を築く力”への期待
SaaS業界において、契約を結んだだけでは意味がありません。
「継続して使ってもらう」「顧客の中で自社製品の価値を定着させる」ことが重要です。
営業出身者が得意とする以下のような能力は、CSでも歓迎されます。
- 初対面でも臆せず会話を広げられる
- 顧客のキーパーソンと関係を築くことができる
- 顧客の“気持ち”に寄り添った対応ができる
特にSaaSでは、導入してからの3ヶ月間が“解約の山場”です。
この時期に信頼を築けるCSは、企業にとって非常に価値があります。
2. ビジネス視点のある提案力
多くのCS職は“サポート係”に見られがちですが、企業が求めているのは能動的に成果を生む人材です。
その点で、営業経験者の「課題を聞いて、整理し、解決策を提案する」力は非常に重宝されます。
企業がCSに求めているのは、たとえばこういう動きです:
- 顧客の利用ログや発言から、業務課題を仮説立てして提案
- 商談ではなく、顧客の“成果”をゴールにしたプランニング
- 顧客の部署・役職によって、伝える言葉や角度を調整する力
つまり、“売る力”の延長ではなく、“考えて伝える力”の応用が求められているのです。
3. 組織を巻き込む“橋渡し役”としての機能
SaaS企業においてCSは、営業・マーケ・プロダクト開発といった様々な部署と連携するハブ的な存在です。
営業経験者は、以下のような強みを持っていると企業側に評価されます:
- 社内外の調整や根回しが得意
- 目的に合わせて必要な人を巻き込む行動力がある
- 顧客の声を“事実ベース”で開発や企画に届ける力がある
CSという職種に求められているのは、“顧客対応”だけではありません。
会社全体の「顧客志向」を強化するポジションとしての視点があるかどうか。
ここが、評価の分かれ目になります。
よくあるズレ:営業の強みを“間違った方向”でアピールする
企業は営業経験者に可能性を感じてはいますが、その強みの活かし方を間違えると評価されにくくなります。
たとえば、以下のようなPRは逆効果になりがちです。
- 「営業目標を〇〇%超えた」→ CSではノルマがない企業も多く、響かない
- 「誰よりもアポを取っていました」→ 能動性よりも“意図のある動き”が評価される
- 「売り込みが得意です」→ CSは売らないからこそ難しい、という構造を理解していない印象に
企業が求めているのは、「営業として何を学び、CSでどう活かすか」まで語れる人材です。
企業側の“理想の営業出身者”とは?
以下のような人物像を持っている営業経験者は、CSポジションで高く評価されやすいです。
- 売上ではなく“成果を生み出すストーリー”を語れる
- 顧客と対話しながら、主語を「自社」→「顧客」に切り替えられる
- 社内で孤立せず、CSチームや開発との連携を大切にする
- “売る技術”を“伝える技術”に翻訳できる
つまり、「自分を売る力」ではなく、顧客が成功する道筋を一緒に描ける力を持っている人です。
小まとめ:企業が見ているのは、“過去”より“伸びしろ”
- 営業経験そのものではなく、“変換できる力”を評価している
- 単なるサポート係ではなく、“顧客の成功を推進する人材”を求めている
- 社内外の関係性を橋渡しできる“ビジネスパートナー”としての立ち回りが期待されている
次章では、CSへの転職を本格的に考える方に向けて、転職前に準備しておくべきことを具体的に紹介します。
焦って動くのではなく、自分の営業スキルを“使える武器”として整えておくことが重要です。
それでもCSに行きたいあなたへ:転職前にやるべき5つの準備
ここまでの章を読んで、「自分にはCSは合わないかもしれない」と感じた方もいれば、
「それでも、やっぱりCSに挑戦してみたい」と感じた方もいるでしょう。
後者であれば、ぜひこの章をじっくり読んでください。
営業経験者がカスタマーサクセスへ転職する際に、“やっておくべき準備”を5つに絞ってご紹介します。
ここを押さえておくだけで、転職後のギャップや苦労がぐっと減るはずです。
1. 自分の営業スキルを“分解して棚卸し”する
「営業スキル」と一言で言っても、その中にはさまざまな要素があります。
たとえば以下のように、スキルを小分けにして整理してみましょう。
- 関係構築力(初対面でも信頼されやすい)
- 提案力(相手の課題に応じた資料やストーリー作成)
- 仮説思考(ニーズを先読みして提案)
- 調整力(社内外のステークホルダーとの交渉)
- ヒアリング力(ニーズや課題を深掘りする質問設計)
これらを棚卸しすることで、「CSに活かせる部分」と「伸ばすべき部分」が見えてきます。
単なる“営業力”として語るのではなく、細かい力をどう変換できるかが大切です。
2. 顧客視点でプロダクトを“観察”する癖をつける
CSにとって、プロダクト理解は命です。
ただマニュアルを読むのではなく、「顧客はこの機能をどう使うのか?」という視点でプロダクトを捉える練習を始めましょう。
たとえば:
- ユーザーインタビュー記事を読む
- SaaSプロダクトの無料トライアルを触ってみる
- 導入支援やサクセス事例をリサーチして、構造を分析する
「どんな課題に、どう役立つのか」「使われない理由は何か」を考えることは、CS的な視点を養うトレーニングになります。
3. 現職で“CS的な視点”を試してみる
すぐに転職しなくても、今いる営業の現場でもCS的なアプローチを試すことができます。
- 契約後のフォローに積極的に関わる
- 導入企業の活用状況を定点観測してみる
- 社内でカスタマーサクセス部署と連携してみる
こうした行動を通じて、**「売って終わりではなく、顧客と一緒に成果を出す」**という感覚を体験できます。
それが、自分にとってCSが“合う仕事かどうか”を見極める判断材料になります。
4. 業務の“あいまいさ”に耐えられるかを自問する
CSは営業以上に、日々のタスクがあいまいになりやすい職種です。
- 正解が1つではない
- マニュアル通りに動けない
- 顧客によってゴールもアプローチもバラバラ
この“あいまいさ”にイライラしてしまう方は、まず自分の特性を見直したほうが良いかもしれません。
自問してみてください:
- 明確な指示がないと不安になるか?
- 自分なりに考えて動くのが得意か?
- 相手ごとに柔軟に対応を変えられるか?
ここでYESが多ければ、CS向きの思考特性を持っている可能性が高いです。
5. 実際のCS社員に話を聞く(ポジショントークに注意)
最後に一番おすすめなのが、リアルなCS職の声を聞くことです。
求人サイトや企業HPでは分からない、現場ならではの悩みや面白さに触れることができます。
ただし注意したいのは、CSの方が語る内容には“ポジショントーク”が含まれていることもある点です。
- 本音と建前を分けて聞く
- 良い点だけでなく、きつい点も聞く
- 異なる企業のCS複数人に話を聞く
こうすることで、「なんとなく良さそう」ではなく、「自分にとって合うかどうか」を冷静に判断できます。
小まとめ:CS転職は準備の質で決まる
- 自分の営業スキルを“変換可能なパーツ”に分解する
- 顧客目線とプロダクト理解をセットで鍛える
- 転職前から“CSっぽい動き”を実践してみる
- 自分の特性と、CSの特性の相性を見極める
- 情報収集はリアルとフラットな視点で
焦って動くのではなく、“意味のある準備”をしてから動くことが、成功への近道です。
営業→CS転職で“幸せになる人”の共通点まとめ
「ノルマのない仕事がしたい」「顧客と長く関わる仕事に就きたい」
そんな気持ちで営業からカスタマーサクセス(CS)へ転職を考える人は年々増えています。
ですが、本当にCS職で満足のいくキャリアが築けるかどうかは、単に職種を変えるだけでは決まりません。
大切なのは、自分自身の思考・行動・価値観がCSにフィットするかを見極めたうえで転職することです。
この章では、CS転職で“幸せになれる人”の共通点を最後に整理し、行動を後押しします。
共通点①:誰かの「成果づくり」を自分の喜びにできる
CSで求められるのは、自分の数字ではなく「相手の成果」です。
目立たないこともあるし、誰かに感謝されるとは限りません。
それでも、
- 顧客が社内で評価される瞬間に立ち会えた
- 提案した施策で利用が定着した
- 解約リスクが高かった顧客を立て直せた
こんな“影の貢献”にやりがいを感じられる人は、CSで確実に幸せになれます。
共通点②:「売る」より「使わせる」ことに価値を感じる
営業は「売って終わり」、CSは「使ってもらって成果が出て、やっと始まり」です。
この構造を頭で理解するだけでなく、気持ちよく受け入れられるかがカギです。
- 提案よりも、活用設計に熱が入る
- プッシュよりも、伴走が性に合っている
- 自社プロダクトを“売り物”ではなく“パートナー”と考えている
そんな思考の人は、CSとして自然に力を発揮できます。
共通点③:あいまいな状況を楽しめる
CSの仕事は明確な正解がないことが多く、定型業務よりも“自分で考える時間”が大半です。
「これは自分で決めていいのか?」「今の進め方で正しいのか?」と迷うこともあります。
ですが、
- 決まりがないからこそ、自分の工夫が活きる
- 成果の定義が曖昧でも、自分で設計できる
- 状況に応じて試行錯誤するのが楽しい
こう感じられる人は、CSのやりがいを何倍にも広げられます。
共通点④:「誰のために働きたいか」がはっきりしている
CSで重要なのは、「顧客」とどう向き合うかです。
何を売るか、どんなサービスかよりも、「誰に何をもたらしたいのか」がぶれていない人ほど強いです。
- ユーザーの働き方を変えたい
- 顧客の事業成長に貢献したい
- 自分の対応が“指名される”ような存在になりたい
そうした意志を持つ人は、迷いなく自分の役割を全うできます。
幸せなCS転職のために——次に踏み出すべきアクション
ここまで読み進めたあなたなら、もう「CSが何か」「自分に合うかどうか」は見えているはずです。
次にやるべきは、“動きながら考える”フェーズに入ることです。
具体的には、以下のアクションをおすすめします。
1. 転職エージェントに相談してみる(SaaS/CS特化)
- 9Eキャリア:CSに特化。スタートアップ〜成長企業の求人が豊富
- CSjob:未経験歓迎・柔軟な働き方もカバー
- マイナビIT AGENT:大手の安心感+20〜30代営業職支援に強い
- JACリクルートメント:ハイレイヤー・外資SaaS系に強みあり
※どれも登録・相談は無料。情報収集だけでもOKです。
2. 現役CSと話してみる
X(旧Twitter)やnote、Wantedlyなどにいる現役CSの方に話を聞いてみましょう。
リアルな話こそ、自分の中の不安や疑問をクリアにしてくれます。
3. 実際に求人を見て“逆算”する
求人票を読むと、自分に足りないスキルや企業の期待値が見えてきます。
今の自分を基準にするのではなく、**“なりたい自分から逆算して準備する”**ことがポイントです。
最後に:キャリアは、「何をやったか」より「どう生きたか」
営業をやってきたあなたは、すでに顧客と向き合う基礎力を持っています。
その力を「売る」から「支える」に変換できれば、CSという新しいフィールドで、大きな価値を生むことができます。
キャリアは、選び方ひとつで、未来の幸福度が大きく変わります。
CS転職はそのひとつの選択肢にすぎませんが、あなた自身が納得して踏み出せるなら、きっと意味ある一歩になります。
動くのは、今です。