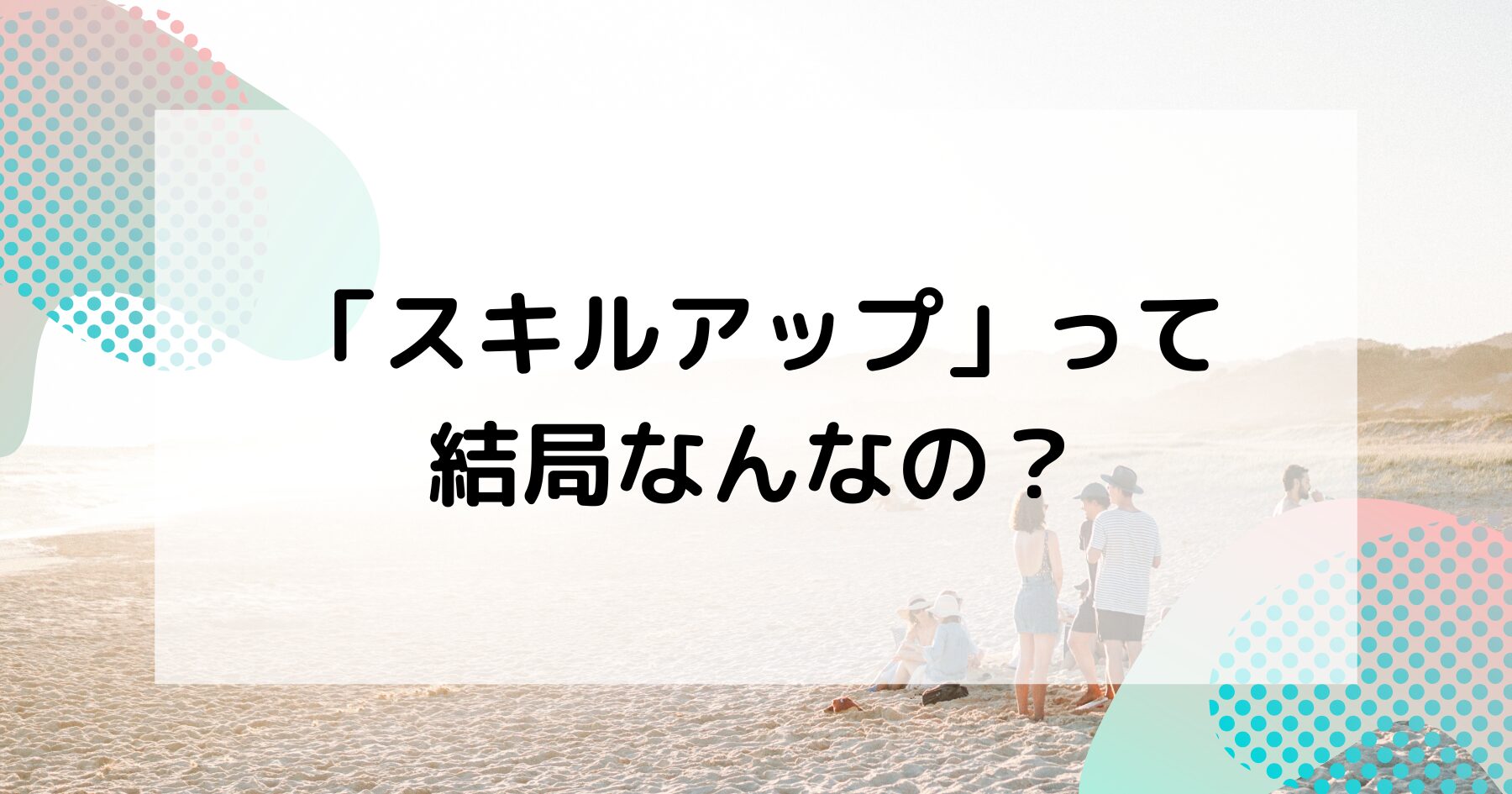「スキルがない」と焦っていたあの頃
営業職として働いていた頃、いつも頭の片隅に「自分にはスキルがないんじゃないか」という不安がありました。
周りは資格を取ったり、マーケやエンジニアに転職したり。SNSでも「キャリアの武器はこれからの時代、○○スキル」といった言葉が流れてきて、自分だけが取り残されているような気がしていました。
転職サイトを見るたびに、職種の要件欄に並ぶ「必須スキル」の文字。
それを見ては、「自分には何もない」と感じていたのを覚えています。
営業しかやってこなかった、が通じない世界
営業経験はそれなりにあって、数字も悪くはありませんでした。
でも、いざ転職を意識すると、「この経験って他の職種にどう活かせるの?」と自信が持てなくなる。
提案はできる。調整も得意。クレーム対応だって慣れている。
それでも、「このスキルを言語化して伝えられない」と感じていました。
だからこそ、「スキルアップしなきゃ」と焦って、資格サイトを覗いたり、ビジネス書を読み漁ったりしていました。
情報ばかりが増えて、手応えは何も残らなかった
Excelの関数、マーケの基礎、ロジカルシンキング。
手をつけたことはそれなりにあります。
でも、どれも“やった気”になるだけで、実際の仕事で活かせた実感は薄かった。
頭の中だけに情報が溜まって、アウトプットの場がない。
スキルを“持っている”つもりでも、“使えている”感覚が持てないまま時間が過ぎていきました。
そのうち、「何を学んでも不安が消えない」という状態になっていきました。
焦りから始めたスキルアップは、空回りしやすい
何かを足そうとする前に、本当は一度立ち止まって、自分の今までの仕事をちゃんと振り返るべきだったのかもしれません。
この頃の僕は、自分の中にすでにあるスキルや価値を見ようとせず、
「新しい知識や資格さえあればなんとかなる」と思い込んでいました。
でも、本当の意味でのスキルは、そういう形では育たない。
本を読んでも、講座を受けても、自信が持てなかった理由
当時の僕は、毎月のように何かしら「スキルアップ」にお金をかけていました。
営業力を高めるための本、マーケティングの基礎講座、ロジカルシンキングのワークショップ。
今思えば、焦って何かを“足さなきゃ”という気持ちでいっぱいだったんだと思います。
でも、どれだけ知識を増やしても、肝心の自信はなかなか育ってくれませんでした。
学んでるのに、何も変わった気がしない
講座を受けたあと、知識はある。ワークもこなした。
けれど、仕事に戻ると相変わらず自分の立ち位置がよく分からない。
たとえば、
- 顧客対応でロジカルに話してみたけど、相手の反応は変わらなかった
- マーケティングの知識を提案に使おうとしても、机上の空論になってしまった
- 学んだフレームワークを使って資料を作ったが、上司にはピンとこないと言われた
「学んでるのに活かせてない」
そんな感覚が積み重なるうちに、次第に「自分にはセンスがないのかも」と思い始めていました。
スキルは持っているだけでは評価されない
この頃の僕は、“持っているスキル”と“活かせるスキル”の違いを分かっていませんでした。
学ぶことで得た知識は、頭の中にはある。
でも、現場でどう使うか、自分の仕事にどう落とし込むかが見えていないと、ただの“知ってる人”で終わってしまう。
それに、スキルというのは、周囲から「それ、助かった」とか「うまいね」と言われて初めて、自分の中で実感として定着するものなんだと思います。
アウトプットのない学びは、自己満足で終わりやすい
スキルアップに関する話でよくあるのが、「インプットばかりで終わってしまう」というケースです。
僕もまさにそうでした。
- ノートにまとめる
- グラフを見て納得する
- ワークをして“理解した気になる”
でも、それを使う場がなければ、ただの情報にしかならない。
アウトプットして初めて、その知識が自分の言葉や判断に変わっていくんだと、後になって気づきました。
自信は学びの中ではなく、行動の中で育つ
いくら学んでも、自分の手で何かを変えた経験がないと、自信にはなりません。
当時の僕に必要だったのは、知識よりも“場数”だったと思います。
だからこそ、次に訪れた転職先で起きた出来事が、僕にとって大きな転機になりました。
そこではじめて、自分が持っていたものの“価値”に気づかされることになります。
転職して初めて気づいた、環境によって変わるスキルの価値
転職を決めた理由は、「もっと成長できる場所に行きたい」という思いでした。
でも正直なところ、「今の自分に何の強みがあるのか」は、よくわかっていませんでした。
面接でも抽象的なことばかり話していた気がします。
けれど、そんな曖昧な状態でも、新しい職場では、思いがけないところで“評価”されることがありました。
前職で当たり前だったことが、「すごい」と言われた
転職先では、カスタマーサクセス職として配属されました。
SaaS系の企業で、業務内容はクライアントとの調整や提案、改善の打ち手を考えるような仕事。
最初は「専門的な知識が必要かも」と不安でした。
ところが、意外なところで周囲に褒められることが増えたのです。
- 資料の構成が分かりやすい
- 顧客の温度感をよく見て動いている
- 社内調整がスムーズで助かる
それらは、前職の営業時代に“当たり前”としてやっていたことでした。
でも、新しい環境ではそれが“ちゃんと価値として伝わる”ようになっていた。
スキルの価値は「職場次第」で変わる
この経験で強く感じたのは、スキルの評価基準は職種や業界ではなく、
その組織の文化や課題によって大きく変わるということです。
たとえば、
- プレゼンがうまい人より、地道に顧客対応ができる人が評価される職場
- 大きなアイデアよりも、細かい改善提案が重宝される文化
- 派手な成果より、チームを支える調整力に感謝が集まる現場
「自分には武器がない」と思っていたのは、ただその価値を認識してもらえない場所にいたからなのかもしれないと気づきました。
他人からの評価で、自分の強みが浮かび上がる
自分では大したことないと思っていた行動が、「助かった」「ありがたい」と言われる。
そうした小さなフィードバックの積み重ねが、少しずつ自信になっていきました。
転職してすぐに“スキルが爆発的に伸びた”わけではありません。
むしろ、自分の中にすでにあったものが、別の場所で“見える形”になっただけ。
でも、その経験こそが、「あ、自分はこれが得意なんだ」と確信するきっかけになったのです。
小まとめ:スキルは持ってるかより、“活かせる場所”で決まる
営業で培った力が、CS職で評価される。
前職では無視されていた工夫が、新しい職場では「よく気がつくね」と言われる。
スキルそのものよりも、“どんな場所で活かすか”によって、
その価値は何倍にも変わるのだと思います。
一番活きたのは、名前のつかない力だった
転職して新しい職場に入ってみて、専門知識や技術的スキルよりも評価されたのは、
意外にも「それ、スキルって言うのかな?」と思うような力でした。
履歴書にも書いてこなかったし、自己PRにも使ってこなかった。
でも、実際の現場では、そういった“名前のつかない力”が仕事の質を左右していました。
たとえば、こんな力
思い返すと、よく周囲から言われていたのはこんな言葉でした。
- 話がわかりやすいね
- そこまで気が回るの助かる
- 初めてでも安心して任せられる
じゃあ、何が評価されていたのかといえば
- 相手の温度感や立場を察して、言葉のトーンを調整する力
- 複雑な内容をかみ砕いて、チームや顧客に伝える力
- 雑多な情報を整理・構造化して、わかる形にする力
どれも、資格や講座では身につけた記憶のないスキルです。
でも、自分が自然にやっていた行動が、他の人には「ありがたい」「助かる」と映っていた。
それが、自分の武器だったんだと初めてわかりました。
名前がつかないからこそ、見落としやすい
こういったスキルは、明確に可視化されないことが多いです。
- KPIに反映されない
- 履歴書に書けない
- 社内で“普通”だと思われてスルーされる
だから、自分でも気づかないし、他人も気づかないまま終わってしまうこともあります。
でも、それが「チームの潤滑油」や「調整役」として欠かせない役割を果たしていたりする。
実は、こういうスキルこそが、“どの職種でも再現性高く評価される力”なのかもしれません。
自分の中の“当たり前”を疑ってみる
大事なのは、「そんなの誰でもやってるでしょ」と思っている自分の行動を、あえて見つめ直すことです。
- 会議の前に資料を読み込んで、想定質問を考えておく
- チャットの文面を、相手の性格に合わせて微調整して送る
- 進捗が遅れそうなとき、早めに報告してリスクを共有する
こういう細やかな行動ができる人は、実はどんな現場でも信頼されやすい。
でも、本人は「スキルアップ」とは思っていないことがほとんどです。
強みは“誰でもできると思ってたこと”の中にある
大きな資格や目立つ成果ではなく、
地味で言語化しにくい行動の中にこそ、自分の強みが隠れていることがあります。
そして、それを活かせる場所に行けば、それだけで評価されるし、仕事が楽になります。
スキルは身につけるものじゃなく、活かして気づくもの
以前の僕は、スキルというのは“自分で努力して身につけるもの”だと思っていました。
本を読んで、講座を受けて、ツールを使いこなせるようになってこそ、スキル。
そう信じて疑っていませんでした。
でも実際には、そうして得た知識よりも、日々の業務の中で何気なくやっていたことの方が、ずっと価値になっていたんです。
強みは、アウトプットの中でしか見えてこない
転職後、周囲に言われて初めて「自分ってこれが得意なんだ」と気づいたことがいくつもあります。
でも、それは自分から発信して、試して、失敗しながらやってみたからこそ気づけたもの。
たとえば、
- 会議のファシリテーションを任されたとき、場を整理する力を評価された
- 提案資料を作る中で、ロジックの構造化が得意だと気づいた
- クライアントとのやりとりで、信頼をつくるスピードが早いと指摘された
それまでの職場では誰も気に留めなかったようなことが、別の環境では“ちゃんと価値として見られた”。
それが、スキルに対する見方を大きく変えてくれました。
自分では「普通」だと思っていることが、一番の武器になる
人は、自分が自然にやれてしまうことほど、「特別ではない」と感じがちです。
でもその“無意識にできていること”こそ、周囲から見れば貴重なスキルだったりします。
- 相手が困っているときに声をかけられる
- 物事を整理して要点をまとめられる
- 新しいツールを触るときに抵抗感が少ない
こうしたスキルは、試験では測れないけれど、現場では圧倒的に求められています。
そして、自分が“得意だと気づいていない”うちは、なかなか自信にもなりません。
フィードバックが“スキルの鏡”になる
自分のスキルを理解するうえで、周囲のフィードバックはとても重要です。
- どんなときに感謝されたか
- どんな行動を「すごい」と言われたか
- 誰かに頼られた理由はなんだったか
こういった言葉の中に、自分では見えないスキルが潜んでいます。
学びっぱなしではなく、実際に行動して、誰かの反応を得ることが、本当の意味でのスキルアップにつながっていくのだと思います。
スキルは、使って、評価されて、やっと“身につく”
ただ知っているだけでは、それはまだスキルではありません。
実際の仕事の中で使い、誰かに評価されて、はじめて「これは自分の強みなんだ」と実感できます。
だからこそ、スキルアップを焦って“足す”前に、
今の自分の中にあるものを掘り下げてみること。
それが、キャリアを変える第一歩になります。
焦って何かを足す前に、今ある自分を掘り下げる
「そろそろ転職したい」
「スキルがないから、何か学ばないと」
そんな焦りを感じたとき、人はつい“足し算”でキャリアを考えがちです。
- 未経験から始められる資格は?
- Webマーケの副業って何から始めればいい?
- スクールに通えば変われるかもしれない
確かに、新しいことに挑戦するのは良いことです。
でもその前に、自分の中にすでにあるものをきちんと見直す時間が、ものすごく大事です。
スキルを探す前に、行動と感情を振り返ってみる
これまでの経験の中で、
- 「この仕事、なぜかスムーズにできたな」と思えたこと
- 「楽しかった」「やってて夢中になれた」と感じた瞬間
- 「もうやりたくない」と思った仕事の特徴
こういった“過去の感情”を丁寧に拾うだけで、自分が向いている仕事のヒントは驚くほど見えてきます。
「何をやったか」より、「どう感じたか」。
そこに、自分の価値観や得意のタネが隠れています。
成果じゃなくて、「評価された行動」に注目する
実績や数字よりも、意外と参考になるのは、周囲からもらった何気ない言葉です。
- 「あれ、すごく助かったよ」
- 「気がきくね」
- 「この資料、わかりやすいね」
そう言われたとき、自分は何をしていたか?
その“行動”に注目することで、自分でも気づいていなかったスキルが見つかることがあります。
他人に聞くのも、有効な自己分析のひとつ
自分の強みや特徴は、自分では気づきにくいもの。
だからこそ、信頼できる上司や同僚に、こんなふうに聞いてみるのもおすすめです。
- 「自分って、どんなとき頼りにされてたと思う?」
- 「一緒に働いてて、いいなと思ったところってある?」
自分の中に眠っている“使える武器”を、他人の視点から掘り起こす感覚です。
学ぶ前に、自分を掘ることが一番の近道
新しいスキルや知識を得るのも大切。
でも、その前に「今の自分はどこに強みがあるか」「何が活きてきたのか」を言語化しておけば、
その先の学びがずっと効果的になります。
キャリアに必要なのは、闇雲なインプットではなく、自分という素材を理解すること。
足すのではなく、すでにあるものを活かす視点が、結果的に最短ルートになることもあるのです。
「スキルアップ」は、自分を使いこなす準備
これまで「スキルアップ」と聞くたびに、
新しい知識や武器を手に入れることだとばかり思っていました。
でも、営業として働き、転職を経て、環境が変わり、人の目も変わっていく中で、
本当の意味でのスキルアップとは、自分を理解し、活かせるようになることだと気づきました。
スキルを足すのではなく、「活きる場」で使うことが大事
資格やスキルを増やしても、それが活きる場所じゃなければ意味がない。
逆に言えば、どんなに目立たないスキルでも、使いどころさえ間違えなければ大きな武器になる。
- 整理するのが得意
- 話すより聞くほうが得意
- 空気を読んで立ち回るのが自然にできる
こういう力は、表立った評価にはつながりにくいかもしれません。
でも、仕事の中で「これ、自分ならできるな」「やっていて苦じゃないな」と思えることは、
間違いなくその人の“強み”です。
「自分を使いこなす」ことができれば、どこに行っても戦える
スキルに名前がついているかどうかは関係ありません。
重要なのは、それを自分が理解していて、必要な場面で使えること。
- 自分の得意な動き方を知っている
- 自分が成果を出しやすい環境を知っている
- 逆に、無理をしても続かない場所もわかっている
それがあるだけで、転職先選びも、日々の仕事の進め方も、大きく変わります。
迷いが減り、自分のキャリアに「こういう方向ならいける」という軸が生まれてくる。
自信は“学びの数”ではなく“納得した経験”から生まれる
いちばん自信がついたのは、知識を得たときではなく、
自分の強みが誰かの役に立っていると感じたときでした。
- 感謝されたとき
- 期待されて任されたとき
- 「これ、君に頼んでよかった」と言われたとき
そんな瞬間を積み重ねて、ようやく「自分には使えるものがある」と思えるようになった。
学んで終わりじゃなくて、実感と納得のある経験が、スキルを“本物”にしてくれる。
今は、そう思っています。
最後に
「スキルアップしなきゃ」と焦っていた頃の自分に、今ならこう言いたいです。
慌てて新しいものを取りにいかなくても大丈夫。
まずは、自分がすでに持っているものに目を向けて。
それを使いこなせるようになることが、最も強くて、信頼できる“武器”になるから。